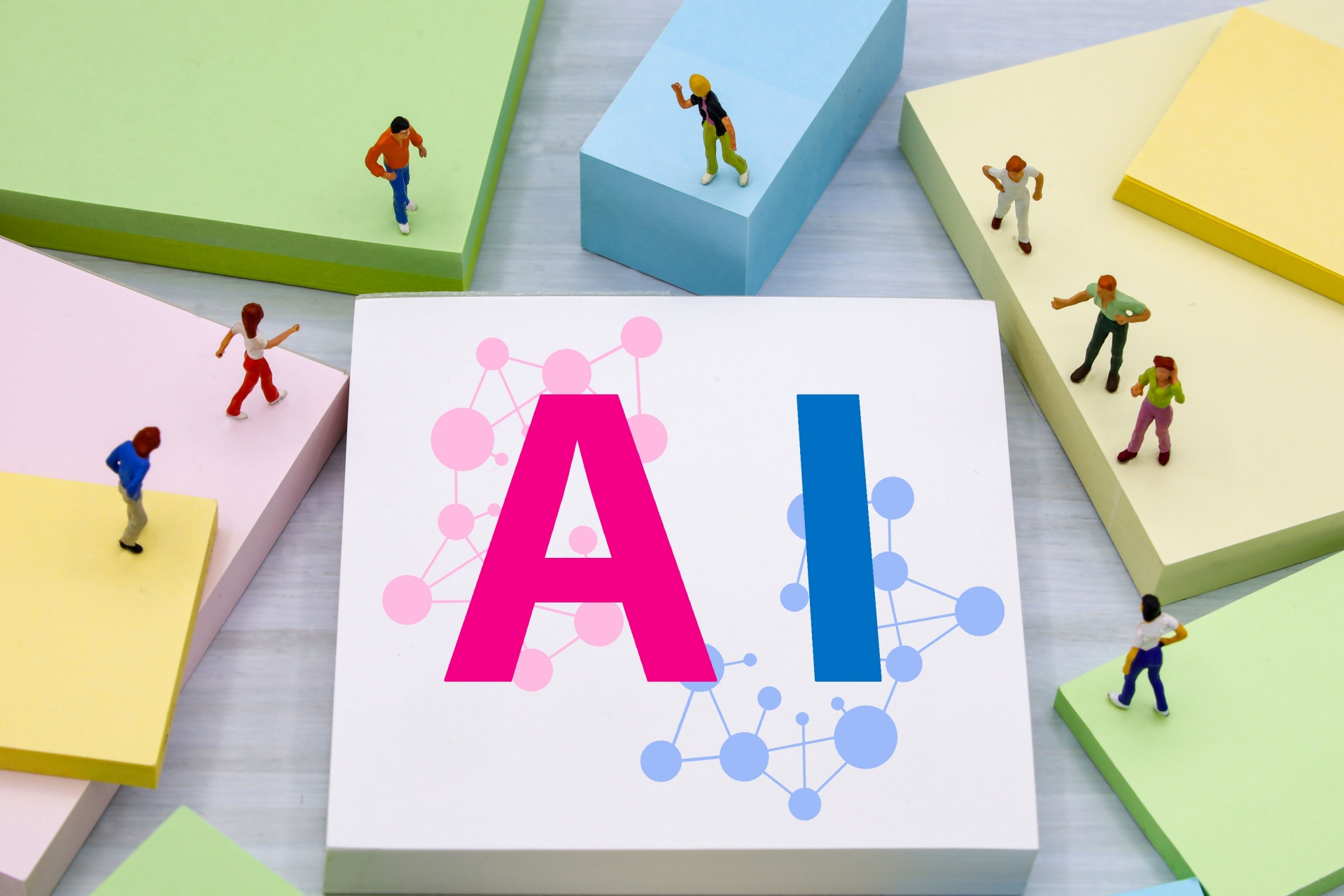公開日: 2025.04.04 更新日:
2025.04.10
介護の人手不足を解決するコミュニケーション革命:AIインカムアプリの可能性
介護業界は深刻な人手不足に直面しており、解決策が急務となっています。本コラムでは、人材不足の根本原因の一つであるコミュニケーション不全に焦点を当て、AIインカムアプリという革新的ツールが現場をどのように変革し、人材定着と介護の質向上に貢献するかを解説していきます。
介護業界の人手不足:危機的な現状と将来予測
日本の介護業界は空前の人材危機に直面しています。厚生労働省の推計によれば、2026年度には約240万人の介護職員が必要となり、現状から約25万人の増加が求められています。さらに2040年度には約272万人が必要とされ、約57万人の不足が見込まれる中、実際の介護職員増加ペースは年間わずか1万人程度。年間6.3万人という目標値からは大きく乖離しています。
現状においても介護の現場では約60%の事業所が人手不足を感じており、特に訪問介護では8割を超える事業所が人材不足を訴えています。この厳しい状況の中で問われているのは、限られた人材でいかに質の高いケアを提供し続けるか、そして何より「今いるスタッフをいかに定着させるか」という課題です。
出典先:厚生労働省|第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
出典先:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」
介護人材の離職要因:「人間関係」が最大の問題

介護職員の離職理由で最も多いのは「職場の人間関係に問題があった」(34%)です。これに「経営方針への不満」(26%)、「他に良い職場があった」(19%)、「収入が少なかった」(16%)が続きます。特に若年層の定着率は低く、3年以内離職率は高卒で49%、大卒で41%と約半数が早期に職場を去っています。
給与水準については改善が進み、介護職員の平均年収は2023年に396.1万円と上昇していますが、全産業平均(506.9万円)との差は依然として110万円以上。政府の処遇改善加算などの施策が進められていますが、賃金だけでは解決しない「働きやすさ」「働きがい」の向上が急務となっています。
介護現場のコミュニケーション不全がもたらす多面的な影響
介護現場におけるコミュニケーション不全は、単なる情報伝達の不備に留まらず、多面的かつ深刻な影響を及ぼしています。
介護スタッフへの心理的・身体的影響
介護スタッフは日々、細やかな観察と迅速な判断が求められる中、コミュニケーション不足による孤立感や不安を抱えています。「判断に自信がない」「助けを求めたいが誰に聞けばいいかわからない」といった状況は強いストレスとなり、心理的負担となります。実際、多くの介護施設でスタッフが「一人で抱え込む」傾向があり、これが精神的疲労やバーンアウトの一因となっています。
また、情報共有が適切に行われないことで、同じ利用者に対して重複した処置が行われたり、逆に必要なケアが抜け落ちたりするリスクも発生します。こうした事態は介護スタッフの身体的負担を増大させるだけでなく、「自分のミスで利用者に迷惑をかけた」という罪悪感につながることも少なくありません。
特に新人スタッフにとって、質問しづらい環境は成長の妨げとなります。「聞けば嫌な顔をされる」「忙しそうで声をかけられない」といった状況が、業務上の不安や孤立感を助長し、結果として早期離職につながるのです。
利用者と家族への安全面・信頼面での影響
コミュニケーション不全は利用者の安全とケアの質に直結します。情報共有が適切に行われないと、利用者の体調変化や好み、生活リズムなどの重要情報が伝わらず、適切なケアの提供が困難になります。例えば、「昨日から食欲が落ちている」「夜間の痛みを訴えていた」といった情報が次のシフトに伝わらなければ、潜在的な健康リスクを見逃す危険性があります。
また、家族とのコミュニケーションにも齟齬が生じやすくなります。「担当者によって説明が異なる」「前に伝えたことが共有されていない」といった状況は、施設への不信感を生み出します。家族が何度も同じ質問をせざるを得ない状況や、重要な情報が職員間で共有されていないことによる対応の矛盾は、深刻な信頼関係の毀損につながります。
施設運営への経営的・組織的影響
コミュニケーション不全が常態化すると、施設全体の組織文化や経営にも深刻な影響を及ぼします。まず、情報伝達の遅延や誤解による業務効率の低下は、残業時間の増加や人員配置の非効率化を招きます。また、「言った・言わない」問題によるスタッフ間の対立や信頼関係の破綻は、チームワークの崩壊につながります。
このような職場環境は、当然ながら高い離職率を招き、新たな採用コストや教育コストの増大という悪循環を生み出します。新しいスタッフが定着する前に辞めていくという状況は、残されたスタッフの負担をさらに増大させ、サービスの質と安全性を低下させる原因となります。
さらに、インシデントやアクシデント発生時の迅速な対応や的確な情報共有が難しくなることで、リスク管理上の大きな課題が生じます。重大事故につながるケースや、問題の早期発見・対処が遅れることで被害が拡大するリスクも高まります。
介護現場のコミュニケーションツール進化の歴史
介護現場のコミュニケーションツールは、時代と共に変化してきました。その進化の過程を振り返ることで、現在のAIインカムアプリの革新性がより明確になります。
ナースコール・PHSの時代と限界

介護施設におけるコミュニケーションの基本は、長らくナースコールとPHSの組み合わせでした。1990年代から2000年代にかけて、多くの施設でナースコールが導入され、利用者からの呼び出しをPHS所持者(主に介護スタッフ)が受けるという体制が構築されました。
しかし、このシステムには大きな限界がありました。まず、ナースコールは利用者から介護者への一方向の通信手段であり、「誰が対応するか」が明確でなく、重複対応や対応漏れが発生しやすい状況がありました。また、PHSによる職員間連絡も一対一の通話が基本で、複数のスタッフへの同時連絡には多くの手間と時間がかかりました。
さらに、公衆PHSは2021年にサービスが終了し、構内PHSも基地局の製造縮小により今後の維持が困難になりつつあります。このような背景から、多くの施設が代替手段の検討を迫られる状況となっています。
別コラム:PHSサービス終了の実態と病院での継続利用について
無線機・トランシーバーの導入と課題

PHSの代替として、一部の施設では無線機やトランシーバーが導入されました。これにより、一度に複数のスタッフへの情報伝達が可能になり、緊急時の連絡手段としての機能も向上しました。
しかし、無線機には距離や障害物(特に鉄筋コンクリート構造の建物内)による通信不良、電波干渉の問題がありました。特に多層階の施設では、階をまたいだ通信が困難なケースも少なくありません。また、「どうぞ」「了解」といった独特の会話スタイルが必要で、形式的・機械的なコミュニケーションになりがちという心理的障壁も存在しました。
短い用件でも無線で全体に知らせることへの抵抗感や、利用者の前での通信に対する違和感も指摘されており、気軽なコミュニケーションツールとしては限界がありました。
スマートフォン・メッセージアプリの活用と問題点

2010年代以降、スマートフォンの普及に伴い、LINEなどのメッセージアプリを業務連絡に活用する施設も増えました。テキストや画像によるリッチなコミュニケーションが可能になり、記録としても残せるという利点がありました。
しかし、介護の現場では「両手が塞がっている」状況が多く、スマートフォンを取り出して操作することは現実的ではありません。また、メッセージの既読確認や返信の遅れは、緊急性の高い業務では大きな課題となります。プッシュ通知を設定しても、現場の音や動きの中で気づかないことも多々あります。
電話機能を使えば即時性は確保できますが、介助中に着信に出られない、複数人への同時連絡ができないといった問題は解決されません。また、個人のスマートフォンを業務で使用することによる、プライバシーやセキュリティ上の懸念も存在していました。
介護記録システムのデジタル化との関係

2010年代後半から、介護記録のデジタル化が進み、タブレットやPCを使用した記録システムが普及しました。調査によれば、介護記録ソフトは85.9%の施設で導入されており、バイタルや食事量、排泄などの記録がデジタルで管理されるようになりました。
しかし、これらのシステムは「記録」に重点を置いており、リアルタイムのコミュニケーションツールとしての機能は限定的でした。記録業務の効率化は進んだものの、現場での即時的な情報共有や連携には別のツールが必要な状況が続いていました。
さらに、介護現場はデスクワークではなく常に移動しながらの業務であるため、固定されたPCやタブレットでの情報確認は現実的ではなく、「記録は後回し」になりがちという課題も残っていました。
このような背景から、「記録」と「リアルタイムコミュニケーション」を効果的に連携させる新たなツールの必要性が高まっていたのです。
介護人手不足の解決策:AIインカムアプリが創る新たな現場

こうした歴史的な課題を解決するのが、スマートフォンとイヤホンマイクを活用した「AIインカムアプリ」です。このシステムは単なる通話機能にとどまらず、AIや音声認識技術を活用した多彩な機能を備え、介護現場のコミュニケーションを根本から変革する可能性を秘めています。
その特長は以下の通りです:
デジタル記録と検索性: 会話内容が自動的にテキスト化され、過去の情報を簡単に振り返り可能
リアルタイム多人数コミュニケーション: 距離や階を超えて、チーム全体での同時会話が可能
ハンズフリー: 両手が塞がった状態でも音声で連携でき、ボタン操作一つで繋がれる
外部システム連携: ナースコールなどの既存システムと連携し、重要通知を音声で連絡
多言語サポート: リアルタイム翻訳機能により、例えば東南アジア出身のスタッフとの言語障壁を軽減
導入施設では、「職員間の意思疎通が格段に良くなった」「新人教育がスムーズになった」「緊急時の対応スピードが上がった」という声が多く聞かれます。特に注目すべきは、単なる業務効率化に留まらず、職場の人間関係や組織文化にポジティブな影響をもたらしている点です。
こうしたツールの進化は、単なる技術革新にとどまらず、介護現場の文化そのものを変える可能性を秘めています。「相手の立場に立ち、共感する」コミュニケーションが技術によって支援されることで、介護の原点である「人と人とのつながり」がより豊かなものになるのです。
インカムアプリ導入による介護現場の変革事例

東京都新宿区の介護付き有料老人ホーム「メディアシスト市谷柳町」では、縦型構造の施設におけるフロア間コミュニケーションの課題を解決するため、AIインカムアプリ「VOYT CONNECT」を導入しました。従来はPHSによる一対一の通話が基本で、職員の所在確認や緊急時の連絡に時間を要していましたが、インカムアプリの導入後は全スタッフとのリアルタイムな情報共有が可能になりました。
具体的な改善点として、ナースコール対応の効率化、服薬管理の改善、外部からの来訪者対応の円滑化などが挙げられます。「例えばナースコールが鳴った時に、3階のナースコールですが、近くにいる人お願いできますか?と全体に発信できます。そうすると他の職員が『行けます』と返事をしてくれる」と介護リーダーの矢野さんは説明します。
また、「職員の口調が柔らかくなった」「新人職員がリアルタイムで指導を受けられるようになった」など、コミュニケーションの質と教育面での効果も表れています。特に注目すべきは、「入ってすぐの新人職員も指示をリアルタイムで受けられるようになりました。『次はどうすればいいですか?』という質問にその場で応えられますし、先輩が『後で確認するね』といったフォローもできる。新人が不安なままで業務を続けることがなくなりました」と副施設長の小山さんが評価しています。
また、「コミュニケーションはどこの施設も課題としてあり、色々な試行錯誤をしていると思うのですが、これ(インカム導入)が最短近道じゃないかな」とも小山さんは評価しています。
導入事例の詳細はこちら
介護の人手不足を総合的に解決する多角的アプローチ
人手不足解消には、AIインカムアプリの導入だけでなく、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。調査によれば、介護記録ソフトは85.9%の施設で導入されている一方、見守りセンサーは56.6%、移乗介助ロボットは22.4%にとどまっています。技術導入が進まない理由として「金銭面」「機能面」「情報不足」「設置スペース」などが挙げられていますが、AIインカムアプリは既存のスマートフォンを活用できるため、比較的導入ハードルが低いという利点があります。
同時に、外国人材の活用も拡大しています。2023年末時点で約2万8400人(2年で5倍増)の特定技能外国人が介護分野で働いており、さらにEPA介護福祉士候補者や技能実習生など多様なルートでの受け入れが進んでいます。言語や文化の壁を超えたチームワークの構築に、AIインカムアプリの多言語サポート機能が大きく貢献しています。
*近年、介護現場の業務効率化と負担軽減を支援する革新的な製品・サービスが次々と登場しています。医療・福祉領域の転職・求人メディア「mikaru」(レバレジーズ株式会社運営)では、「介護現場の業務効率化&負担軽減に取り組む企業・組織に注目!」と題した記事において、自社のインカムアプリの他にも介護者にとって業務効率化を目指せる製品がいくつか紹介されているので、ぜひ参考にしてください。
【mikaruについて】『いい仕事、いい未来、ミツカル』をスローガンに、医療・福祉領域の全国の求人をまとめて掲載する転職・求人メディア。医療福祉領域で働く方に向けて役立つ情報も提供しています。
・mikaru公式サイト:https://mikaru.
・mikaru求人一覧:https://mikaru.jp/
介護現場の人手不足解消に向けた導入・運用のポイント
AIインカムアプリ導入に際しては、厚生労働省や自治体のICT導入支援事業を活用することで、初期コストを抑えることができます。政府は介護現場のICT化を推進しており、多くの地域で導入補助金が用意されています。
実際の導入に当たっては、以下のステップが有効です:
現状課題の具体化:どのような場面でコミュニケーション不足が生じているか明確にする
導入目的の共有:単なるツール導入ではなく、「なぜ」「何を変えたいのか」を全スタッフで共有
段階的展開:一部の部署やシフトから試験的に導入し、成功体験を積み上げる
フィードバックの収集と改善:現場の声を反映した継続的な使用方法の最適化
まとめ:介護の人手不足を解決する鍵はコミュニケーション革新
介護現場における深刻な人手不足は、新たな人材確保だけでなく、現場のコミュニケーション革新によって乗り越えられる可能性があります。AIインカムアプリは、単なる業務効率化ツールを超え、職場の人間関係改善、チームワーク強化、そして何より介護スタッフの「働きがい」創出に貢献します。
「相手の立場に立ち、否定ではなく共感する」コミュニケーションを技術で支援し、介護の質を高めることは、人手不足の悪循環を断ち切る重要な一歩です。厚生労働省が示す2026年度までの約25万人という介護人材確保目標を達成するには、テクノロジーの力を最大限に活用し、限られた人材がより質の高いケアに注力できる環境づくりが不可欠です。
AIインカムアプリの導入によって、介護職員が「ここで働き続けたい」と思える職場づくりを進め、持続可能な介護サービス提供体制を構築していきましょう。